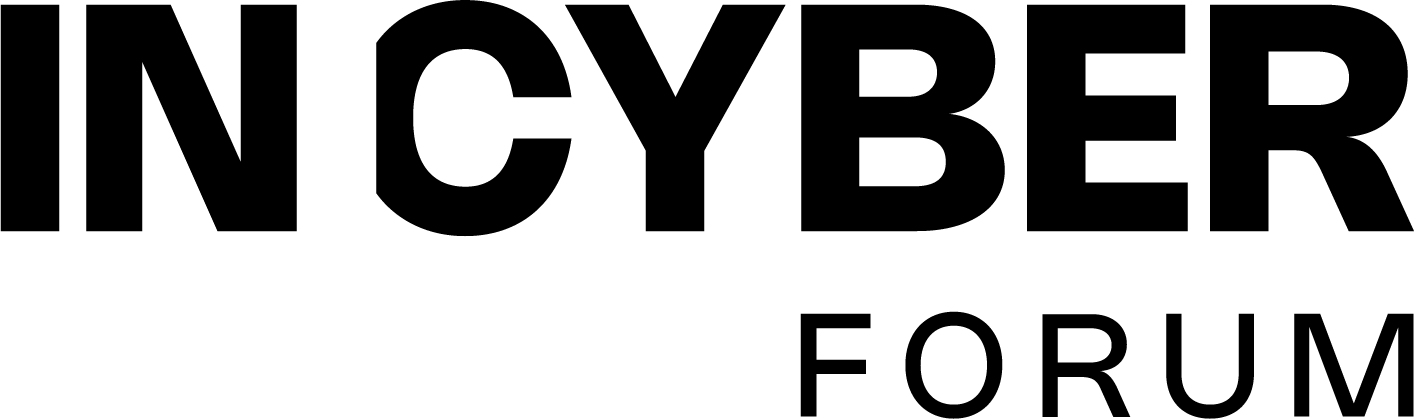はじめに
経済安全保障を考える上でサイバーセキュリティは、
日本においてもこの課題が明確に浮き彫りになってきています。
この一年、日本は高度化するサイバー攻撃の急増に直面しています。国の中枢機関から基幹産業に至るまで、多様な分野で被害が相次いでいます。
名古屋港を麻痺させた2023年6月のランサムウェア攻撃は、日本のデジタル基盤が戦略的に狙われている現実を改めて浮き彫りにしました。
これらの出来事は、国民の信頼を大きく揺るがし、長らく遅れていた意識の高まりを促す契機となりました。
グローバルの視点からは、日本のサイバー防衛について「不十分で、対応が遅すぎる」との指摘もあります。
そして、海底データケーブルに大きく依存する日本にとって、脆弱性はもはや理論上の懸念にとどまらず、国家の存続にも関わる深刻な課題となっています。
しかし、状況は変わりつつあります。
サイバーセキュリティは、2022年に改訂された国家安全保障戦略において、5つの最重要課題のひとつに位置づけられました。
日本は今や、受け身の対応に追われるだけではなく、再構築に乗り出しています。
国内セキュリティソフトへの約100億円規模の投資から、政府システム全体の強化に至るまで、日本はデジタル主権の確立に向けた基盤を着実に築きつつあります。
サイバーセキュリティの課題は、もはや技術的な側面にとどまらず、地政学的な課題でもあります。
日本はアジアにおける民主主義の最前線に立ち、強い影響力を行使する隣国と対峙しています。こうした状況に対応するため、日本は国際的な連携の枠組みを築いてきました。
日米サイバー対話、フィリピンとの三国間協力、ASEANとの「日ASEANサイバーセキュリティ・コミュニティ・アライアンス」、さらにはNATOや英国とのサイバー協力、その広がりはグローバルに及んでいます。
この課題が喫緊であることは、もはや疑いの余地がありません。
サイバー脅威は国境を越えて押し寄せ、政策の対応を待ってはくれません。
日本で大規模なサイバーセキュリティイベントを開催することは、時宜を得た取り組みであるだけでなく、不可欠な一歩です。
知恵を結集し、レジリエンスを高め、日本が単に脅威を認識しているだけでなく、確かな備えを整えていることを世界と攻撃者に示すことになります。
サイバー防衛は、もはや選択肢ではありません。
それは日本が切り拓くべき、次なるフロンティアなのです。